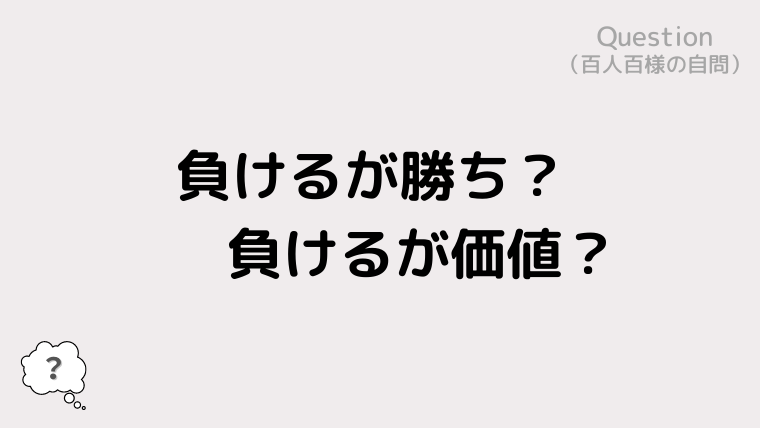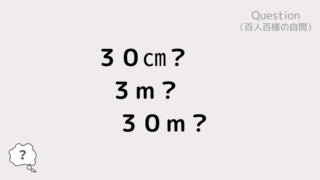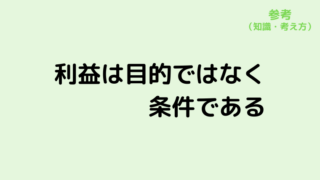「負けるが勝ち」という言葉についてのお話です。
個人的には「負けるが勝ち」より、「負けるが価値」の方が使いやすいと感じています。
何のために「負ける(=争いを避けたり、譲歩したりする)」のか?
その部分に着目します。
「負けるが勝ち」の意味
「負けるが勝ち」
辞書で調べてみると、
【負けるが勝ち】
一時は相手に勝ちを譲り、しいて争わないのが、結局は勝利をもたらすということ。
出典:小学館 デジタル大辞泉
とあります。
Google検索のAIによる概要では、
負けるが勝ち「負けるが勝ち(まけるがかち)」とは、一時的に相手に勝ちを譲る方が、最終的には大きな勝利につながるという意味のことわざです。つまらない争いを避け、大局的な視点を持つことで、長期的な利益や総合的な勝利を得ることを指します。意味合い●一時的な損失を受け入れるその場の勝負に勝つことにこだわらず、相手に譲ることで、将来的に大きな不利益を避けたり、有利な状況を作り出したりする。●全体的な視点短期的な損得ではなく、物事の大局や長期的な視点で判断することが重要であることを示唆しています。●賢明な判断感情的に争うのではなく、相手に勝つことで得られるかもしれない一時的な満足よりも、争いを避けることによる最終的な勝利や利益を重視する、賢明な判断を意味します。使用例
●子どもに対して「お兄ちゃんだから負けてやりなさい。負けるが勝ちでしょう」と諭す際に使われます。●小さなことで相手と争うのではなく、相手に譲ることで全体の調和や自身のより大きな目的達成につながる場合に用いられます。
Google検索のAIによる概要
と出てきます。
実践ではしっくりこない
頭で理解する分には、特に問題ありません。
言葉自体は難しくないので、先ほどの解説もすんなり入ってきます。
しかし、日常で使おうとすると、しっくりこないことがよくあります。
それは我慢の限界を超えてしまい、私の精神状態として「負ける」ことができないケースではありません。
私がしっくりこないのは、「負ける」という行為ではなく、「負けるが勝ち」という言葉の方です。
個人的には、「勝ち」という部分が引っかかります。
「負ける(=争いを避けたり、譲歩したりする)」ことは、その行為だけをとりあげれば気が進まないことも多いと思います。
それでもあえて「負ける(=争いを避けたり、譲歩したりする)」ことを選ぶのは、それを代償として得たいものや、守りたいものがあるからでしょう。
先ほどの解説の中で言えば、
この下線の部分が、それに相当すると思います。
この解説では、「将来的な不利益の回避」や「物事の大局」といった視点も書かれています。
「負けるが勝ち」ということわざは、「その場で勝つこと」か「最終的な勝利」かといった、単なる「勝ち負け」だけの問題ではありません。
ところが日常で実践しようとすると、どうしても「勝ち」という言葉に引っ張られます。
口に出していなくても、文字として書いていなくても、心の中でつぶやいている時、「負けるが勝ち」という字面が脳裏に浮かんできます。
『別に勝ち負けの問題じゃないよな~』という場面でも「負けるが勝ち」ということわざを思い浮かべると、「勝ち」という言葉によって「勝ち負け」の発想に引きずられます。
その結果、適切な選択をとれなくなってしまいます。
「負けるが勝ち」から「負けるが価値」へ
私は「勝ち」という言葉と相性が合わず、「負けるが勝ち」という言葉のままでは活かせませんでした。
知っていても理解していても活かせないので、そのままではもったいないですね。
そんな自分を踏まえて、いつの頃からか少しアレンジして使っています。
「負けるが勝ち」でなく、「負けるが価値」として。
「勝ち負け」の発想を土台とすると、私の場合は「負ける(=争いを避けたり、譲歩したりする)」能力をあまり発揮できません。
しかし、自分の「価値あるもの(=大局的に得たいもの、失いたくないもの)」を土台とすると、同じ場面でもだいぶ違ってきます。
ちなみに私は、「負ける」ことに限らず、日々の活動全般で「勝つこと」が原動力になりにくいため、「価値あるもの(=大局的に得たいもの、失いたくないもの)」を土台として自分を動かしています。
近い感覚をお持ちの方は、私と同じタイプかもしれません。
具体的行動とは別に、土台の発想にも着目してみてください。